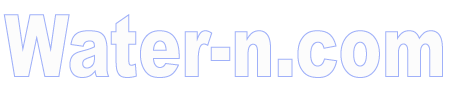「都市計画×インフラ」でミライのまちを描こう
2025年6月11日の水マネ大学は、都市総合研究所 専務理事(都市計画協会 審議官)の佐々木晶二さんに「都市計画×インフラ:都市計画をインフラマネジメント、まちづくりにどう活かすか」をテーマに講義していただきました。
日本ではこれからも人口が減り続けていくことは避けられません。そうした未来に向けて、まちをどう作り直していくかを今から考え、行動していく必要性を強く感じます。
まちが新しい形になれば、当然ながらインフラも新しい形、新しいあり方に変わっていくはず。ですから、これからはますます「都市計画」と、上下水道などインフラの計画を融合させて、まちづくり全体のあり方を描いていかなければなりません。
ですが佐々木さんは「都市計画制度には、インフラを維持管理する観点が乏しい」と指摘します。小学校などハコモノ系の公共施設の再編が進んでおり、一方で上下水道などインフラ系では長寿命化計画が進んでいますが「両者の計画はバラバラに策定されており、空間的に統合されていない」。そのため、統廃合して廃校になった小学校周辺の道路や上下水道が長寿命化されたというケースもあるそうです。これでは、まちの未来像が描けません。
持続可能なまち、ひいては持続可能な日本を実現するために「まずはまちを空間的に広げないこと」が重要だと指摘されていました。空間的に町が広がって、そのたびに上下水道のパイプを伸ばしていけば、上下水道の維持管理コストは高騰し、上下水道サービスの持続可能性も危うくなります。パイプにつながなくてすむオフグリッド型の上下水道代替システムの導入を条件化するなど、市街化調整区域での開発を抑制する厳しい条件を設定することで野放図に町が広がることを規制できるのではないかと指摘されていました。
もっと詳しく知りたい方はぜひ水マネ大学2026年度で仲間になってくださいね。