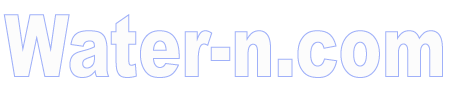建設業をクリエイティブにする「創注」って何?
2025年6月25日の水マネ大学は、RRP Lcc. 代表(東洋大学大学院公民連携専攻 客員教授)の矢部智仁さんに「『新・建設業』への転換」をテーマに講義していただきました。
「新・建設業」とは、誰かが作った仕事(注文)を請け負う「受注」ではなく、自ら仕事(注文)を創造する「創注」型の建設業のことだそう。生みの苦しみはありそうですが、受注型よりクリエイティブでトキメキが増えそうです。
では、なぜ今、「新・建設業」を目指さないといけないのでしょうか。建設業界取り巻く市場環境は厳しさを増しているように感じますが、実はデータをひもとくと2014年から市場(出来高ベース)は継続的に上昇しており、一方で業者数はちょっと減っているため、結果として1社あたりの仕事は増えている。意外にも恵まれた状況にあるそうです。
しかし、問題は資材高と人材不足によって失注がおきていること。2030年には労働供給が644万人も不足するそうです。DXやAIなどによって生産性を上げる、今いる人のリスキリング、地元で働く人を地元で育てるなどの人材育成と、人材を集めるために建設業の魅力アップが急務であり、その第一歩が「新・建設業」への転換だと指摘されていました。
「新・建設業」を目指すには、まず「昭和脳」を捨てること。
「昭和脳」というのは、モノ(供給)を作れば売れる(需要が創造)という「供給→需要」の順番で行動すること。
昭和脳:供給→需要創造(×うまくいかない)
これに対し今後は、売れる規模(需要)を見極め、それにふさわしい規模のモノ(供給)を作るという「需要→供給」の順番で行動すること。そのためのヒト・モノ・カネを集める役割の一端を「新・建設業」が担いうるとおっしゃっていました。
今後:需要創造→供給(新・建設業が活躍する場)
また「新・建設業」に必要な5つの力を紹介いただきました。
1、マーケティング
2、プロデュース
3、プランニング
4、ファイナンス
5、オペレーション
もっと詳しく知りたい方は、まもなく発売の矢部さんの著書「変われ!地域ゼネコン」(日経BP)を読み、そして水マネ大学2026年度で仲間になって、クリエイティブにトキメキましょうね。