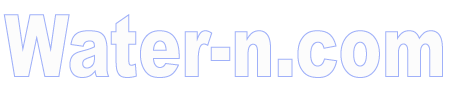「会計」はインフラを伝える武器になる
2025年8月27日の水マネ大学は、有限責任監査法人トーマツにお勤めで公認会計士の資格を持つ藤巻祐輔さんに「今さら聞けない公営企業の財務諸表(基礎編)」を、同じく香田浩一さんに「今さら聞けない公営企業の財務諸表(応用編)」をテーマに講義していただきました。
上下水道をはじめとするインフラを運営すると、収入を得たり、モノやサービスを買って支払ったり、カネの出入りがあります。これは普通の企業と全く同じです。インフラだけが特別ではありません。
このカネの出入りをしっかりと記録するのが「会計」であり、会計の解像度を上げることで経営が見える化される。そこからはじめて経営改革が始まると藤巻さんは指摘されていました。
会計には「account for」、つまり「説明する」という意味があるとのこと。企業の財務的な側面を説明するものであり、インフラの関係者には会計を通してインフラ事業の財務的な側面を説明する責任があるとおっしゃっておられました。
インフラを知ってもらう手段として「広報」を思い浮かべる方が多いと思いますが、それと同様に、あるいはそれ以上に「会計」による情報開示は重要なのだと改めて胸に刻みました。
香田さんからは「公営企業会計で覚えておいてほしい8箇条」を紹介していただきました。
1、公営企業会計は何のために必要?
→上下水道料金がいくら必要かを計算するため
2、上下水道料金の計算はどうすればいい?
→損益計算書を見ればいい
3、費用=料金なので、利益はゼロでないといけない?
→インフラ資産維持を目的とした利益発生は認められている
4、利益はいくらまで認められるの?
→資産維持費として説明可能な額
5、料金計算だけをしっかりやれば安定経営は実現できるの?
→損益計算書は資金収支と整合しないため、ファイナンス(資金繰り)の検討は必要
6、損益計算書の非資金損益の意味がわからないのですが・・・
→減価償却は資金留保効果の意義がある(ただし、耐用年数上の課題あり?)
7、その他経営に影響を与える会計判断はありますか?
→総括原価「費用-収益」の収益に含める範囲と会計処理の影響は大きい。具体的には一般会計繰入金の会計判断
8、料金についてその他の課題も教えて
→料金負担を利用者別(住民、企業など)にどう配分するか
料金値上げ(200%など)をどこまで行うか
新技術活用(スマートメーターなど)の可能性
もっと詳しく知りたい方はぜひ水マネ大学2026年度で仲間になってくださいね。